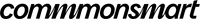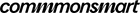南琢也|グラフィックデザイナー
インタビュアー:國崎晋(RITTOR BASE ディレクター)
國崎: 南さんはいつから坂本さんの作品のデザインに関わるようになったのですか?南: 2007年に山口情報芸術センター[YCAM]で坂本さんと(高谷)史郎さんがインスタレーション作品「LIFE - fluid, invisible, inaudible...」を制作・展示されたとき、ポストカードとポスターのデザインをしたのが最初です。もともと史郎さんとはダムタイプで一緒に仕事をする機会が多く、このときも史郎さんに“ちょっとデザインして”って言われて参加したんです。その後、『async』のジャケットでも史郎さんのアートワークを主軸にしたデザインを頼まれました。直接坂本さんからデザインの依頼をいただいたのは『12』のジャケットが最初ですね。國崎: 『12』は李禹煥(リ・ウファン)さんによるドローイングが印象的ですが、あのドローイングを使用することは最初から決まっていたのですか?南: はい。なので僕が担当しているのはタイポグラフィー…… 文字組みの部分です。僕は絵は描けないんで、イラストレーションとかのデザインはしません。オリジナルのビジュアルを作るというよりは、文字をどう組んでいくかというところに興味があるんです。國崎: ご自身でオリジナルのフォントを作成することもあるのでしょうか?南: 文字を組んでみて、既存のフォントだとうまくフィットしないことが多いので、文字の1つ1つのフォルムを整えていく作業はよくやっています。ほぼほぼこのフォントでいけそうだなっていうのがあるんですけど、どうにも気に入らないところがあって、そこを修正したフォントを作成して使っています。國崎: 『Opus』のジャケットデザインはどのような経緯で担当することになったのですか?南: もともと配信ライブとして制作されたときに、タイトルと字幕やエンドロールの文字組みを担当したんです。その流れで『Opus』としてパッケージ化される際にジャケットのデザインも担当することになりました。國崎: 配信ライブそして映画の映像はモノクロでした。ジャケットもそれを意識してモノクロ基調になったのでしょうか?南: 当然、そうなると思いました。映像というのは光をどう留めていくかという作業ですよね。映像における“無”は黒なので、黒をベースに展開していくっていうのをあの映像を見た瞬間から決めていました。國崎: 『Opus』のCD、アナログ、DVD、Blu-ray、そしてBOXセット『Opus - objects』の箱には、非常に質感の高い黒紙が使われています。南: パッケージで使った黒紙はいろいろな種類をテストして決めたものです。黒紙ってすぐ傷だらけになるんです。傷が目立たないようにするコーティング方法はいくつかありますが、commmonsさんが作られるものは常に環境に配慮されているので、ポリプロピレンを使わずに傷が目立たないようにするコーティング方法について検討を重ねました。その結果、保護するという意味も兼ねてCDではジャケット本体に紙を巻いてカバーにしています。CDにカバーを付けるっていうのは、史郎さんと一緒に『LIFE - fluid, invisible, inaudible...』のDVDジャケットを作っていたときからやっていることで、本のようなパッケージを目指して作っています。CDやレコードは音を記録するメディアですけど、本は文字を記録するメディア。CDにカバーを付けることでその両方を兼ね備えています。國崎: 黒紙に浮かび上がるようにタイトルが印刷されているように見えますが、どういう処理がされているのでしょう?南: “Opus”という文字は黒箔です。そして“Ryuichi Sakamoto”にはシルバーを使っています。黒い空間の中で箔とシルバーとで響き方を変えているイメージですね。音楽で言うと違う楽器が演奏されているような感じです。國崎: CDやBlu-rayが収められているトレイも黒で統一されています。南: リパックというスウェーデンで開発されたトレイです。通常はバージンパルプ100%の白紙を使用しているんですけど、今回は黒で作ってほしいと無理なお願いをしました。この黒紙は英国のFSC認証を取得した紙で、カーボンオフで黒くした紙なんです。『Opus』のデザインをするにあたって、映像のように情報の無い部分は全部黒くしたいなと思っていたんです。だから、“ブックレットも黒紙で作りませんか?”って提案したんですが、さすがに可読性的にも問題があるし、やり過ぎだろうということで通常の白い紙になっています。國崎: BOXセット『Opus - objects』には、アナログレコード、ブックレット、『Opus』収録時に坂本さんが実際に使っていた20曲分の譜面を完全複製したもの、さらには匂い香が収められています。それらをまとめて1つの箱に収めるのは大変だったのでは?南: いろいろなメディアが1つのパッケージに入ってるっていうのは、昔のカセットブックのような面白さがありました。BOXセットのブックレットを上製本にしたのも、文字を記録するメディアとしての存在を際立たせ、レコードや楽譜といった音の記録メディアと対比させたかったからです。ただ、もちろんメインは音源であるレコードだと思いましたので、その素材であるビニールよりもモノとしての強度が強いものを入れると負けちゃうので、匂い香についてはバランスを考えながらちょうど良いサイズのものを緒方慎一郎さんにご提案いただきました。楽譜に関しては『Opus』収録時に坂本さんが使われていたものを複製し、鉛筆や赤鉛筆で書き込まれた筆跡もそのまま残しています。國崎: レコードのジャケットでは写真をフィーチャーしていますね。南: CDやDVD・Blu-rayのジャケットと同じく、黒の中にどう響かせていくのかというのを、サイズや文字のポジションをいろいろな比率を計算しながらパズルのようにグリッドを決めて割り出していきました。國崎: CD、DVD、Blu-ray、アナログ、BOXセット、いずれも質感が高く、商品というよりアートピースのような趣があります。南: 商品パッケージを作るというよりは、坂本さんが発した音を記録・保存するメディアをデザインしていくイメージで作りました。“音って何なのかな?”みたいなことを考えるわけなんですけど、音って拡散し、減衰し、聴こえなくなっていくじゃないですか。ですが、音のエネルギー自体はそのまま残る…… 空気や水など媒介するものとの摩擦で熱エネルギーに変換されるらしいんですよ。だとすると、発信された音のエネルギーは失われることがなく、ずっと続いていく。坂本さんから発せられた音が響きながらずっと継続して続いていくような、エネルギーが失われずに続いていくようなイメージですね。國崎: 今回のパッケージは、失われず続いていく坂本さんのエネルギーをビジュアル化したデザインであったと?
南: 音とビジュアルの関係という意味では、僕は藤本由紀夫さんの「phono/graph」というプロジェクトに参加していて、音と文字とグラフィックの関係性をテーマに作品制作をしているんです。音と文字やグラフィックの関係と言っても、グラフィックで音を演出するようなものではなく、音や文字やグラフィックが音楽でいうポリフォニーのように作用する…… 音響空間と視覚空間が重層的に作用する中で生まれる表現の可能性を研究するプロジェクトです。そこにはたくさんのメンバーが集まっていて、藤本さんの言葉…… 例えば“私たちは今、目で音を聴き、耳で絵を見ている”をキーワードにしながら作品を制作していくんです。なので音と文字やグラフィックの関係っていうのはそのプロジェクトを通して常に考えていまして、坂本さんが『async』以降に取り組まれていたことにすごく近いというか親和性を感じていました。それがそのまま今回のパッケージデザインにも現れていると思います。
南琢也|グラフィックデザイナー
京都市立芸術大学大学院造形構想修了。成安造形大学教授。
川上拓也|編集
インタビュアー:村尾泰郎(音楽/映画評論家)
村尾: 川上さんはどういう経緯で『Opus』に参加されたのでしょうか。川上: 空音央監督とはこれまで何本か一緒に仕事をやっていて、プライベートで食事に行ったりもしていたんです。それで一昨年(2022年)、監督から電話があって、坂本(龍一)さんの演奏を撮影して映画にするプロジェクトがあるんだけど編集をやってくれないか、と頼まれました。これまでの仕事を通じて、監督の仕事への向き合い方とか好みはだいたいわかっていたので軽い気持ちで引き受けたんです。村尾: 撮影前に監督は編集についてどんな話をされたのでしょう。川上: そんなに細かい話はしませんでしたが、「映画」として編集して欲しいということでした。ミュージック・ビデオみたいな感じではなく。村尾: 川上さんにとって「映画的な編集」というのはどういうものですか?川上: ショットの選択だと思います。ミュージック・ビデオの場合、音楽に合わせて映像を編集しますが、映画はショットを優先させる。今回はAカメ、Bカメ、Cカメの3つのカメラで撮影して、それぞれが撮った素材をスイッチングして(映像を切り替えて)いるのですが、Aカメのショットが“生きて”いたら1曲ワンショットでもいい。ただ、だからといってショットを絶対的なものにすると音楽とそぐわなくなることもあるので、音楽との関係を壊さないようにしながらショットを選択していきました。村尾: 音楽と映像の関係性を意識した編集だったんですね。音楽を楽しむだけではなく、坂本龍一という人物が浮かび上がってくる作品に仕上がっていました。川上: 編集する前に素材を全部観た時に、坂本さんとピアノ、坂本さんと音との関わりを描いたドキュメンタリーだと感じたんです。なので、本作はコンサート・フィルムというよりも、ドキュメンタリー映画と考えて編集しました。そして、最初に編集して見たものを議論の土台として、監督と話をしながら一緒に直して行くという感じでしたね。村尾: 1曲1曲、趣向を凝らした映像と照明で撮られていますが、その繋ぎ方にも工夫が凝らされています。暗転になったり、演奏以外のシーンが挿入されたり。そうした繫ぎ方は川上さんに任されていたのでしょうか。川上: 任されていた部分もあったかと思います。全部繋いだものを何回も観直して、その度に初めて観るお客さんの気持ちになって、ここはもう少し時間をあけて曲の余韻を味わえるようにした方がいい、とか、考えながら繋ぎました。演奏の合間にミニ・シーンが入っているじゃないですか。坂本さんが「Tong Poo」を練習したり、ちょっと疲れたような様子を見せたり。あれはカメラマンが独自の判断で撮影したものだと思いますが、そういうものを曲間に入れることで、映画としての流れが作れないかと思ったんです。村尾: そういう演奏以外の映像がライヴのMCみたいな役割を果たして、坂本さんの集中力の高い演奏からくる緊張感を和らげていますね。川上: 最初に曲だけ繋いで通して観た時に、集中度が高すぎて(笑)。このままだとすごく疲れるな、と思ったんですよ。村尾: 1人のカメラマンが撮っていたら、坂本さんとの関係性が密になりすぎて息苦しく感じていたかもしれませんが、3人のカメラマンの映像が使われていることで緊張感を感じさせながら表情豊かな映像になっているように感じました。川上: 監督と撮影監督のビル(・キルスタイン)との間で、撮影に入る前に綿密に話し合って撮影設計が決め込まれていたと思います。だから映像素材はどれも素晴らしく、監督とビルが思い描いたものをできるだけ崩さずに編集しようと思いました。ビルは技術的にはもちろんですが、カメラワークもすごいんですよ。まさにスーパーカメラマン。Bカメの石垣求さんも映画の撮影監督で、使える画を常にしっかり押さえている。何が必要かを心得ている間違いない素材なんです。Cカメの小田香さんは映画監督で自分で撮影もするんですけど、自由な感性で撮っていて。ショットの選択に迷った時はビルのショットを選べば安定するし、何かアクセントが欲しい時は小田さんのショットを入れてみる。安定した素材ばかりだったので編集作業はとてもやりやすかったです。村尾: 3人のカメラマンの個性が撮影に反映されているんですね。川上: カメラのポジションは最初に設計された通りだと思いますが、その位置からどう撮るかは各自に任されていたのではないかと思います。「Aqua」のビルのカメラがすごくて。曲の構成に合わせてカメラが動いていくのですが、そのカメラワークがずば抜けているんです。その話を監督にしたら、「Aqua」はビルがいちばん好きな坂本さんの曲らしくて、ビルの気持ちがカメラに出ているんでしょうね。あと、映画『トニー滝谷』のサントラの曲「Solitude」が演奏されるじゃないですか。『トニー滝谷』はドリー(横移動撮影)を多用しているのが特徴の映画なんですけど、石垣さんのカメラは「Solitude」の時、ずっとドリーで撮っているんですよ(笑)。村尾: 密かにオマージュを捧げていた(笑)。小田さんのショットで印象的なものはありました?川上: 坂本さんを正面から撮ったショットがあって。カメラを上下に動かして撮っているんですけど、坂本さんがフレームから外れてもどんどんカメラを上げて壁を撮ってる(笑)。本人を目の前にして、すごい勇気だと思いました。あと、映画の最初に光の中を埃のようなものが舞っている映像があるじゃないですか。あれも小田さんが撮ったものなんです。最初はすぐに演奏シーンから入る予定だったのですが、監督と話し合って、その映像を頭に入れることにしました。村尾: そんな風に、予期しないものを作品に取り入れる柔軟さが監督にはあったわけですね。川上: そういえば、「Bibo no Aozora」で坂本さんが間違えるじゃないですか。そのあとに撮った、間違わずに最初から最後まで演奏したテイクもあって、現場からもらった記録シートではそれがOKテイクになっていたんです。でも、監督は失敗してやり直すテイクを選んだ。これまでパフォーマーとして映し出されていた坂本さんが、一瞬素顔を見せる印象的な映像で僕は好きなんですけど、実は演出されていた可能性があるんですよ。村尾: というと?川上: 去年、山形国際ドキュメンタリー映画祭に監督と一緒に行ったんですけど、そこで監督と飲んでいる時に、あのシーンは坂本さんが演奏する間に、監督が〈ちょっとだけ失敗してくれない?〉と言った、という話を聞いたんです。お酒の上での冗談かもしれませんが。村尾: もし、そうだったとしたら坂本さんの名演技ですね!
川上: 編集している時は、〈失敗しているけど面白いから使って〉と言われたんですけどね。どっちが本当かは、監督が明らかにするまで永遠の謎です(笑)。村尾: 本編に使われなかった素材で印象に残っているものはありますか?
川上: 本番の撮影で「よーい、アクション!」という声をかける担当の方がいたんですけど、坂本さんはその方の「アクション!」という声では演奏には入れないみたいで。「そうじゃなくて、こうだよ!」って「アクション!」の言い方を指導するんですよ、ちょっとイラついた感じで。疲れていたこともあるんでしょうけど、そのやりとりがとても人間臭くて面白くて(笑)。その映像を使うかどうかで意見が割れたんですけど、結局、外すことになりました。村尾: 演奏のきっかけになる掛け声なのでナーバスになりますよね。川上さんは坂本さんが演奏をする姿をご覧になってどんな印象を受けました?川上: 一言で言うと「すげえな」と思いながら編集をしていました。体力的には大変だと思うんですけど、音楽に向き合っている姿に一瞬の隙も見せない。〈この演奏をフィルムに残す〉と言う強い意志が伝わってきて、気軽に引き受けたけど生半可な気持ちではやれないぞ、と思いました。一度、撮影現場にもお邪魔したのですが、VENICEという大きなカメラを使っていて、1曲ごとに照明を変えたり、ドリー用のレールを引いてカメラのポジションをセッティングし直したりするんです。そんななかで、1曲ごとにピアノにちゃんと向き合えるというのはさすがだなと思いました。村尾: 今回、この映画を通じて、改めて坂本龍一というミュージシャンに対して感じたことや発見はありました?川上: 今回、編集作業を通じて坂本さんのいろんな表情を見たのですが、一番印象に残ったのは楽しそうな顔なんです。辛そうな時もあるんですけど、映画全体を通して坂本さんは楽しそうに演奏されている。これだけ世界的に評価されて、これだけ長い間、音楽活動をされてきて、しかも、病気なのに、ピアノと一対一で向き合って演奏するのを楽しんでいることに驚かされました。村尾: 最後まで音楽に触発されていた。まさに芸術は長く、人生は短い、ですね。
川上: ほんとそうですよね。坂本さんのピアノの響きを聴きながら、今も演奏をしながら何か新たな発見をしているんだろうな、と思って。そこに終わりなき探究心みたいなものを感じたんです。それが僕にとっての発見であり、希望でした。
川上拓也|編集
2012年からフリーランスとしてドキュメンタリー映画を中心に録音技師、編集者として活動。作り手によるドキュメンタリー批評雑誌『f/22』編集委員。主な作品は『風の波紋』(16/小林茂監督)、『台湾萬歳』(17/酒井充子監督)、『アイヌ・ネノアン・アイヌ』(21/ラウラ・リヴェラーニ&空音央監督)、『マイ・ラブ 日本篇 絹子と春平』(21/戸田ひかる監督)、『百年と希望』(22/西原孝至監督)、『重力の光 祈りの記録篇』(22/石原海監督)、『はだかのゆめ』(23/甫木元空監督)、『二十歳の息子』(23/島田隆一監督)、『きのう生まれたわけじゃない』(23/福間健二監督)など。
ZAK|サウンドディレクター/エンジニア
インタビュアー:國崎晋(RITTOR BASE ディレクター)
國崎: レコーディングについて、何か坂本さんから注文はありましたか?ZAK: NHK509スタジオは響きが良いので、それを期待していると言われました。あとリヒターがバッハ「平均律クラヴィーア」をお城で録ったレコードを教えてもらって…… 坂本さんが若い頃によく聴いていたそうで、「こんな感じが好きなんだよね」と。今まではそういうリファレンスを出す人じゃなかったので、ちょっとビックリしました。若い時の体験を自分のアウトプットに反映したいっていうのはすごく素直な気持ちだし、そういう境地なんだなとも思いました。國崎: 実際の収録について伺いたいのですが、ZAKさんはレコーディングやコンサートのとき、ピアノを置く位置をとても細かく調整されますよね。ただ、今回の収録は映画の収録であり、撮影チームの意向もいろいろあったと思います。録音側と撮影側で何かコンフリクトしたことはありましたか?ZAK: 置き場所については任せますと言われました。ただピアノの蓋は付けた状態にしてほしいと。音のことを考えると蓋は取った方がいいんですが、映像的なことを優先して、取らずにレコーディングしました。実際に様々な反射が鏡のような役割をしていて、映像を立体的で美しいものにしていると思います。國崎: ピアノの蓋を外すと音が良くなるのはなぜですか?ZAK: 音が開放的になるんです。もともとピアノの蓋はステージから客席に向けて音を広げていくためのものですから、録音の場合はあまり必要無いと思っています。蓋があるとちょっとレゾナンスが生じるし、ピークも出ます。もちろん、皆さんはそれも含めてピアノの音として聴き慣れていると思うんですけど、僕はもうちょっとクリアな方が好きなんです。坂本さんもライブや録音で蓋を外されることも多かったですし、無い方が圧倒的にマイキングしやすいんですよね。マイクを自由なところに置けるし、マイクの上に蓋が無いことによってレゾナンスも起こらないから、より自然な音が録れる。ピアノという楽器の音を全体としてちゃんと録りやすいんです。國崎: 蓋を付けるということは譲りつつ、ピアノの置き位置はZAKさんの意向通りになったのでしょうか?ZAK: 最終的には僕が希望したところより少し壁側に寄って、向きも反対になりました。國崎: ZAKさんはレコーディングやコンサートで、ピアノのキャスターの下に木のスペーサーのようなものを挟むことが多いですが、今回も使いましたか?ZAK: はい。クラビベースという木でできているチューニングベースで、役割としてはインシュレーターに近くて、余分な音の鳴りを減らすために使います。おにぎりのような形をしていて、各頂点の方向に音が逃げるので、向きを変えることによってピアノ自体の音の詰まりなどを逃がしたりトーンを調整します。ピアノの複雑な機構と置かれている空間とのバランスを取るためにピアノ自身の位置や、足の角度を調整してニュートラルな状態に持っていくように流れをよくする感じです。…… 気功や整体っぽい感覚ですね。人に例えると立ち方や姿勢を調整して声の出方を良くするみたいな。國崎: ピアノの音を録るため、マイクはどのようなセッティングにしたのでしょう? そこでも撮影チームとの折衝が必要でしたか?ZAK: 位置の変更は見え方の都合で曲ごとにありました。だからすべての曲でマイクのセッティングは少しずつ変わっています。國崎: 撮影に支障がないよう、設置するマイクの本数を少なくした方がいいとは考えませんでしたか?ZAK: 最初はそう思いました。それこそ坂本さんがリファレンスとして教えてくれたリヒターの録音はワンポイントステレオで録られているような音でしたし、プロダクションの方からもそういう録音でどうかという話もありましたが、現場では何が起こるか分からないですし、映画になるなら、きっとDolby Atmosにしようという話も出てくるだろうと思い、マイクはたくさん置くことに…… 合計で27本立てたのかな。國崎: 27本もマイクを立てて、撮影チームは大丈夫だったのでしょうか?ZAK: 本数が多いことについては問題が無かったです。逆にビジュアル的にも面白がってもらえました。國崎: ダンパーペダルの音を拾っているという話がありましたが、『Opus』ではダンパーペダルの動作音がとても大きく聴こえました。ピアノってこんなにゴトゴト音がするのかと驚いた方もいらっしゃると思います。ZAK: 別に坂本さんの踏み方が荒いわけじゃなく、実際に近くで聞くとあれくらいペダルの音がするんですが、今回のミックスではその音を強調しているのも確かです。というのも、あの音を含めて坂本さんの演奏だと思うので。國崎: 昔に比べると坂本さんはピアノを弱音で弾くことが多くなりましたよね。それで相対的にダンパーペダルの音が大きく聴こえる…… 恐らくご本人も耳を澄ましてピアノを弾かれるようになったからこそ、ダンパーの音も聴きながら演奏されていたのかもしれませんね。ZAK: そうだと思います。多分、ダンパーペダルの上げ下げを記譜しようと思ったら、できると思います。上げる速度まで坂本さんは体感で調整していたと思います。國崎: ダンパーペダルと対照的に、坂本さんの呼吸音は『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』として配信されたときと比べ小さくなっていました。ZAK: 配信のときに呼吸音を大きく残したのは2つ理由がありました。1つはダンパーペダルの動作音と同様に、呼吸音や衣擦れの音も含めて、その場で起こっていることを全て音楽の一部としてとらえたいという意図がありました。もう1つは、配信された当時、坂本さんはご存命で、最後の力を振り絞って演奏していたため、その存在感とその瞬間の生々しさを感じさせ、同時に生命の儚さと尊さを静かに、強く訴えかけるような気持ちもありました。続く『Opus』のミックスでは『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』より更に長尺になったため、情報量をフォーカスするために呼吸音は減らしていて、Blu-rayではプライベートに何度も再生されることを考慮してさらに減らしています。國崎: たくさんのマイクを使った録音だったわけですが、それらを使ってどういうミックスを作ろうとされたのでしょうか?
ZAK: 曲ごとに違うものにしました。ラストで流れる「Opus」は環状に置いた12本のマイクで収録した音をメインにしていて、ほかにも数曲それと同じような音像がありますが、あとは曲ごとにかなり違いますね。國崎: 普通でしたら音像を1つ決め、全部の曲でそれを踏襲するやり方になると思いますが、そうはしなかったと?
ZAK: 普通のライブ映像だったらそれでいいかもしれませんが、やはり映画なのでもっと強い作品として見えた方がいいだろうと思い、1曲ごとに変えていったんです。國崎: 具体的に何をポイントとして曲ごとに変えているのですか?ZAK: 編集が終わった映像とマッチするものを探していくやり方です。音先行ではなく、映像とのバランスで空間やリバーブ感を決めていきました。それが顕著に出ているのは冒頭の「Lack of Love」で、カメラが坂本さんに近づいていくのに合わせて、音量をだんだん上げています。だからすごく生っぽい仕上がりになっていると思います。國崎: それこそ映画のサウンドトラックを作っているようなミックス方法なんですね。映像に対して合うような音を、何十本ものマイクで収録されたトラックのバランスで都度都度変えていくという。ZAK: はい。なので曲の中でもクローズアップのシーンと離れているシーンとでマイクのバランスを変えています。例えば「Andata」では最初はちょっと離れた音像で始まるんですが、途中で結構寄るシーンがあるので、その時は音も近く聴こえるようにしています。國崎: クローズアップのシーンではピアノの近くに立てたマイクの音量を上げ、遠景だと遠くに置いたマイクを上げていく?
ZAK: そうですね。近くのマイクを上げるだけじゃなく、遠くのマイクの音量を減らすことで近い音に聴こえるようにすることもあります。國崎: 作品としての純度をどんどん高めるために必要な演出を施していかれたと?
ZAK: ええ。なので坂本さんの本来の演奏を一般的な録音の仕方で聴かせるという形からは離れているかもしれませんし、それに違和感を感じる人がいるかもしれませんが、その”場”を体験するという点から、没入すれば逆にそれが正しいと思うような仕上がりになっているとも思います。NHK509スタジオという空間の容積としては変わらないけれども、自分が見ている視座が変わっていくような感じですね。
ZAK|サウンドディレクター/エンジニア
幅広く多彩な音楽活動に携わり、Alva Noto、BOREDOMS、Brian Eno、BUFFALO DAUGHTER、FISHMANS、FRICTION、Jeff Mills(Spiral Deluxe)、Oneohtrix Point Never、青葉市子、UA、菅野よう子、坂本龍一、三宅純などのライブ、レコーディングを手掛け、現代美術家の村上隆との『SUPER FLAT』以降の作品の共作や、『維新派』『飴屋法水』『NODA MAP』『マームとジプシー』などの演劇の音響、犬童一心監督の『名付けようのない踊り』などの映画音楽監督、近年は片山正通の手掛けた『虎ノ門ヒルズ T-MARKET』など公共施設や店舗の音響も手掛けている。
酒井武|ピアノ調律師/コンサートチューナー
インタビュアー:國崎晋(RITTOR BASE ディレクター)
國崎: 「ピアノ調律師/コンサートチューナー」とはどのようなお仕事なのでしょうか?酒井: ピアノが使われるコンサートやレコーディングの現場で、ピアノの鳴り方をいろいろな面から調整する仕事をしています。ピアノの調律は音の高さを合わせるだけでなく、ピアノのメカニックの部分であるアクションを調整する作業も行います。ピアニストから鍵盤をもっと深く沈みこむようにして欲しいとか、逆に浅くして欲しいとか、あるいは重くとか軽くとか、タッチに関していろいろと感覚的なリクエストをいただくので、ピアノのメカニズムのいろいろなパーツを調整してそれに応えていきます。その作業のことを「整調」と言います。さらに音色を整える作業もあり、それは「整音」といいます。音の高さを合わせる「調律」、アクションを調整する「整調」、そして音色を整える「整音」、この3つをまとめて「調律」という言い方になっています。國崎: 酒井さんはどのような経緯で坂本さんのピアノを調律するようになったのですか?酒井: 坂本さんのケースはとても珍しくて…… 普通、ピアニストは自分のピアノを持ち運べませんので、ホールやスタジオの備品を使うのですが、坂本さんはレコーディングやコンサートのとき、常にご自身のピアノを現場に持ち込んでいたんです。坂本さんが所有されているピアノがヤマハピアノだったので、代々ヤマハの調律師が坂本さんのピアノの調律を担当しており、僕は2010年から2015年の5年間を担当していました。國崎: 坂本さんのピアノの調律を行う場合、他のピアニストとは異なるような注文はありましたか?酒井: 僕が最初に坂本さんの調律を本格的に担当したのは、2010年に大貫妙子さんと作られた『UTAU』のレコーディングのときでしたが、そのときに「真っ直ぐな音…… ピーンと鳴るような音が欲しい」と言われました。ピアノは1つの鍵盤につき弦が3本ある音域があって、それらをどう合わせるかによって“ポーン”とか“フワーン”というように、いろいろな音の形が作れるのです。例えばショパンを弾く場合だと“フワーン”となるように調律しますし、バッハだとカチッとした音にします。坂本さんの場合はそのどちらでもなく、“ピーン”という揺らぎのない音。コンサート会場の最後列まで真っ直ぐに届く音を望んでいました。「静かな森の中に湖があって、湖面が全然揺れてない状態」とおっしゃっていましたが、そのためには単純に3本の弦をぴったり合わせればいいというわけではありません。ぴったり合わせると減衰が早くなってしまう…… 合い過ぎて“ピーン”じゃなくて“ポン”ってなってしまうのです。國崎: 近年、坂本さんはピアノの音の消え際を聴くのが好きとおっしゃっていました。そのためには真っ直ぐな音を必要とされていたのでしょうか?酒井: はい、響きを聴きたいから音を長く伸ばすにあたり、揺らぎがないようにしたかったのだと思います。ただ、そのためにはオクターブごとに平均律が本当に精密にできてないといけない。そうでないと次のオクターブで崩れていってしまいます。坂本さんはピアノの88鍵を全部使うので、それぞれのオクターブを精密に合わせていくにはかなり時間がかかります。國崎: 坂本さんは鍵盤のタッチに関してはどのような好みがあったのでしょう?酒井: タッチに関しては、2010年から2015年に僕が担当していた時と、『Opus』の録音をした2022年とでは話がちょっと違います。2010年から2015年頃の坂本さんは、ピアニッシモからフォルティッシモまでコントロールできる体力があって、音色は暖かく落ち着いた音が好みでした。その音を出すために、それに合うタッチにしていました。ところが『Opus』収録のとき、初日に僕が前のイメージのまま整調したら、指慣らしをされた坂本さんに呼ばれて、「酒井さん、すごく僕のことを分かってくれていて、とてもいい調律なんだけど、今僕は闘病中でタッチが変わってしまったんだ…… 」と。体力が落ちていた坂本さんにとって、タッチが敏感過ぎたんですね。それで少し鈍くする方向で整調していきました。國崎: 「整音」についても以前と変化した部分は?酒井: 音色については「暗い音を出したい」と言われました。ピアノの音にはたくさんの高次倍音が含まれていて、それにより生じるブリリアントな音色は特にクラシックの演奏に必要なのですけど、暗い音を出すためにはその成分を抑え減らしていく方向で整音しました。國崎: 具体的にはピアノのどこを触るとブリリアントな成分を抑えられるのでしょう?酒井: ピアノは鍵盤と連動しているハンマーが弦をたたくことで音が鳴る仕組みになっていますが、そのハンマーの固さを調整することで、ブリリアントな音からソフトな音までさまざまな音が出せます。ソフトにするためにはハンマー外側の羊毛の部分を、針が付いている工具で刺していきます。そうすると羊毛がほぐれて柔らかい音になっていきます。逆に硬くしたい場合は鍵盤を連打して羊毛を固めたり、紙やすりをかけて削ったり、硬化剤を使って硬くすることもあります。國崎: 『Opus』収録の際、整音は曲ごとに行ったのでしょうか?酒井: 全部の曲というわけではないですが、曲ごとに弾かれる音域が少しずつ違いますからその辺りを調整することはありました。ピアノは弾きこんでいくと、さっきも言いましたようにブリリアントになっていく…… どんどん鳴るようになりますので、その辺りのバランスを直していきます。収録は一週間ほどかけて行ったのですが、実は日々音は変わっているのです。坂本さんの望んでいる音が分かってきたというか、僕の耳が変わっていったというのもありました。『Opus』のコンセプトのひとつとして時間の流れがあるので、坂本さんも「ずっと同じじゃなくていいんだ」っておっしゃっていて、僕もどんどん良くなるように毎日調整を重ねていきましたね。國崎: 収録順と映画での曲順はほぼ一緒と伺いました。酒井: はい。なので、曲を追うごとにだんだん楽器が鳴ってきています。最初にその状態のピアノが作れればいいんですけど、その時間があってこそなので。逆に曲ごとのそういう聴き方を楽しんでいただければ嬉しいです。國崎: 「20180219 (w/prepared piano)」はプリペアードピアノによる演奏でした。映像にもありますように坂本さんが施したのですよね。酒井: はい、弦をクリップで挟んだり、いろんな小物を差し込んだりしていましたね。國崎: プリペアードピアノは、ピアニストが偶発的な音が欲しくて行うケースが多いですが、「20180219 (w/prepared piano)」は本来のピアノとは違う倍音を得るために坂本さんが「整音」をしているように見えました。酒井: その通りですね。ちゃんと狙いがありました。恐らく何回も試したのを踏まえ、クリップの挟み方などのノウハウが坂本さんにたまっていたのだと思います。出鱈目にやっているのではなく狙って出していましたね。國崎: 完成した『Opus』をご覧になって、酒井さんはどんな感想を持たれましたか?
酒井: 2022年末に「Playing the Piano 2022」の配信を観たときと、映画『Opus』とで印象がかなり変わりました。お亡くなりになったという意識で観ているからかもしれませんが、より純度が高いというか、ドキュメンタリー性を減らし、作品性が高まったと思いました。冒頭、カメラが坂本さんの後ろ姿をとらえていますが、あのアングルは僕がいつも見ているアングルなのです。コンサートでのいつもの自分の立ち位置から見える景色なのでドキドキしましたね。國崎: 坂本さんの最後のピアノ演奏として残るかもしれないという意味で、大変なプレッシャーだったとは思いますが、あらためて振り返るといかがでしたか?
酒井: 普通のコンサートとは違い、事前の配信もするし、最終的には映画のための収録で、坂本さんからも「これは大切な収録だから酒井さんにお願いしたんだ」とお話をいただき、嬉しい反面、気を引き締めて頑張らなければならない現場でした。2015年以降、僕は海外に転勤となって坂本さんの調律から離れていたのですが、今回また呼んでいただけたのは、僕が坂本さんの調律をやっていた5年間は『UTAU』の収録やツアーだったり、「Playing the Orchestra」など、ピアノを弾かれる機会がものすごく多い時期で、そのときの印象が良かったからだとスタッフの方から伺いました。それこそ最初の『UTAU』の収録のときは、“真っ直ぐな音”と言われてもすぐに対応できず、「もうちょっとこうして」みたいに言われていたのが、だんだんと何も言われなくなり、僕も坂本さんが求めている音が分かってきて、担当していた時期の後半3年くらいはピアノについては何も言われることがなくなりました。クラシックの現場で得たものに加え、学ぶことが多く、そういう意味では坂本さんに育ててもらったという意識があります。そんな坂本さんにとって最後になるだろうという収録で再び呼んでいただけたのは本当に嬉しかったです。一週間かけた収録は、やっている時は大変だったのですけど、終わってみると本当に充実した毎日でした。
酒井武|ピアノ調律師/コンサートチューナー
神奈川県伊勢原市出身
空音央|監督
インタビュアー:佐々木敦(思考家/批評家)
佐々木: そもそもなぜライブ演奏を音央さんが映画にすることになったのですか?空: 発端は2020年に行われた配信ライブで、僕は一応カメラ担当で入っていたんですけど、実際に配信されたものの出来が良くなかったんです。で、2022年の3月か4月に“コンサートみたいなものを映像化したいから何かやってくれ”という話が来たんです。僕はちょうど自分の長編映画の準備段階で忙しい時期だったんですけど、本人の病状がどんどん悪化していたので、やはり後悔はしたくなかったのでやることにしました。佐々木: ということはディレクションというか、どういうルックのどういう作品にするかを考えるところから始めることができたわけですね。演奏を撮影して映画にするといっても、本当にいろんなアプローチがあり得えますが、こういう形の作品にしようとした理由は?空: 最初は悩みました。ドキュメンタリー的な映像…… 最期の日々的なものを撮ってコンサート映像に挿し込んだりとか、アーカイブ映像を持ってきたりとか、インタビューを挟んだりとか、もしくはコンサートのビハインド・ザ・シーンみたいな、ちょっとほっとしている雰囲気の映像を挟むとか、いろいろありますよね。でも、ある時点でそれはいらないって決めたんです。佐々木: それはすごく大きな選択だったと思うんですけど、なぜそうされたのですか?空: 自分が肉親という特権的な距離にいるからこそ撮れる映像を入れれば、もちろん本人の人間性みたいなものが見えてくるんですけど、実はそれって既に結構やられている。だから僕にできる一番のことは、ちゃんとコンサートを撮ることかなと。実際、コンサートを疑似体験するっていうのを目的とした途端、いろいろスムーズにいったんです。とにかく現場で起こったことを撮るだけにして、どれだけこの映画を通してコンサートを疑似体験できるかに徹する感じ。そうと決めたら僕の仕事は単純というか…… 今でも思っているんですけど、僕は本当にこの映画の監督なのかなと。音楽の方はほとんど口出しせず、映像だけ任せてもらって…… 映像も本当に信頼しているビル・キルスタインっていう撮影監督に任せ、あとは素晴らしい照明デザインの吉本有輝子さん、信頼する編集の川上拓也さん、カメラオペレーターの石垣求さん、小田香さん、そして録音とミックスのZAKさん。みんなすごく信頼しているスタッフなので、ほとんど任せた感じなんです。佐々木: 信頼できるスタッフに任せたとはいえ、監督として何かテーマ設定をされたのではないですか?空: そうですね、やはり核に据える何かがないとブレるので、“身体性”をテーマとしました。それを決めたというのが監督としての自分の仕事ですね。そうしたらすぐにほかの要素が決まりました。例えば、なぜ白黒の映像にしたのですかとよく聞かれるんですけど、それも身体性を考えたからです。白黒にすることで手の皺やピアノの質感を浮かび上がらせることができる。あと、最も本質的な映画の喜びは何か?みたいなことを考えたとき、僕は炎を見てるような光と影が揺れている感じ…… しかもそれがリズムに乗ってというのが一番だと思っていて、それを白黒でやるとレジェの『バレエ・メカニック』みたいな初期のダダ作品とか、アルタヴァスト・ペレシャンのモンタージュ理論に近いような、白と黒の影のダンスみたいになっていくかなと。しかもズームインすればするほど、影が大きなスクリーンを巡るだけみたいになって抽象性が増すかなと。佐々木: 抽象性というか、今回かなりストイックな作品になることは最初から分かっていたと思います。NHKの509スタジオで撮影されたわけでお客さんはいない。広いNHKのスタジオにピアノだけで、ものすごく要素がミニマルになってしまうじゃないですか。それを長編映画にするとなると映像設計が必要というか、ずっと同じ感じで行くわけにもいかないですよね。何か過去の映像作品で参考にしたものはありましたか?空: 具体的に参考になったのは『グレン・グールドをめぐる32章』という、いろいろな切り口でグレン・グールドを見せる映画でした。ピアノを撮る場合って結構アングルが限られるんですけど、こんな撮り方があるんだという発見がありましたね。もうひとつはやはりグールドものなんですけど、1960年代にレナード・バーンスタインがやっていたアメリカのTV番組にグールドが出演したときの映像Ford Presents "The Creative Performer" (1960)です。オーケストラと一緒に演奏している映像で、白黒なんですけどちゃんとライティングされていて、ハリウッドさながらのミュージカル映画みたいなカメラの動きが素晴らしいんです。こういう感じに撮れば長く観ていても飽きないなと。佐々木: そういうリファレンスがあった上で、実際にはどのような撮影プランを考えたのですか?空: 観客がいないというのを逆に生かして、いかに観客の主観的な体験をカメラで模せるかを考えました。例えばホールのコンサートって大体何百人と一緒に聴くものですけど、次第に自分の世界に入っていって、気付いたらすごく近くにいるような錯覚に陥ることってありますよね。逆に広大なメロディに差し掛かった時に本当に風景が見えてくるみたいな感覚に陥ったりも。そんな感じで曲に寄り添った撮影をしたいと思ったんです。佐々木: 曲そのものが持っているイメージとか展開を踏まえ、そのドラマツルギーみたいなものを映像に反映させたということですか?空: まさにその通りですね。ショットの構成を曲単位でやりました。分かりやすい例で言うと「Aubade 2020」という曲は全部固定カメラでやったんですけど、ビルに“これは淡々とした毎日の生活みたいな曲だから、小津っぽく撮ってくれ”ってお願いしました。佐々木: 観客の主観的な体験を模すようなカメラということでしたが、オープニングの「Lack of Love」は舞台袖からのカメラで、観客目線とは異なりますよね。空: そこだけは例外というか、あれは僕の視点なんです。本人がピアノを弾いてる時に僕が一番見ていた視点は背中からだったので、それを最初にしました。何がもとになってるかっていうと、坂本龍一がまだ元気だったころ、“ご飯ができたから呼んできてよ”って母親に言われて僕が階下のスタジオに呼びに行くんですけど、大体ピアノを弾いているかパソコンをいじってるんです。で、ピアノを弾いていると邪魔しにくい…… 泣いたりしているんですよ、自分の曲で。ホントに恥ずかしげもなく…この人逆にすごいなと思ったりするんですけど、ご飯ができてるから声かけなくちゃって、“ここにいるよ”みたいに自分の存在を感じさせて…… オープニングのシーンはそういう視点なんですよね。佐々木: 実際、「Lack of Love」は最初は結構距離があるところから背中を追っていって、それがここまで寄るんだっていうくらいのとこまで寄って、ピアノの音もだんだん大きくなる。実際にはカメラとマイクで収録しているわけですけど、人みたいだなと思ったんですよね。演奏している人が気付いていないのを後ろからそっと行く感じ。それが冒頭にあることによって没入させるというか、まるで自分が本当にその場に立ち会って演奏していくさまを見続けている感じになる。その一方で、これは監督の音央さんの視点というか主観でもあるなって思ったんですよ。主観を観客の視点に開け渡すっていう部分と、音央さん自身のパーソナルな感覚みたいなものが二重になっている感じで、それがすごく感動的でした。空: そこまで見ていていただけると嬉しいですね。佐々木: 全編白黒にした理由は先ほどうかがいましたが、その中でも光…… 照明の変化が印象的でした。空: 撮影の構成はほとんど曲単位でやっていたので、全体の流れは照明で作りました。薄暗いところから始まり、4曲目、5曲目で朝3時とか4時に水平線がちょっとだけ明るんでいる感じになり、「Aubade 2020」でだんだん白んで朝になったと知らされる。佐々木: 光の変化によって“時間”というテーマも浮かび上がってきますよね。坂本さんの最後のシアターピースは「TIME」でしたし、ご本人にとっても大きなテーマだと語られていました。面白いなと思うのは、この映画は103分の長さで、その103分の中に照明で表されているもっと長い時間がたたみ込まれている。さらに言うと撮影は何日にもわたって行われたわけですから、1つの作品の中に複数の時間の層があるわけです。実際に撮影は何日間行われたのですか?空: 8日間プラス準備に1日でした。佐々木: 8日間の撮影は連続していたのですか?
空: はい。なるべくセットリスト順に撮ったんですよ。それができたから照明による時間変化とかも考えやすく、クリエイティブな作業ができました。佐々木: 8日間の撮影を経て、いろいろな映像が撮れたと思うのですが、それを編集していくとなるとかなり選択の幅があって大変だったのではないですか?
空: 実はそんなに大変じゃなくて…… 編集者の川上拓也がすごい優秀だっていうこともあるんですけど、彼に言われたのは、僕とビルの撮影の設計があまりにも決まり過ぎていて、これ以外に編集のしようがない…… “こう使ってほしいって映像が言ってる”と言われました。佐々木: 肉親である音央さんだからこそ、神格化したくないという気持ちもあったと思いますが、実際このように1本の映画として仕上がったら、そこからまた新たに伝わるイメージとか増幅されるイメージもあると思います。そこは多分すごく悩まれたんじゃないですか?
空: ええ…… 実際どんな人間だったかということなんですが、死んだ後にいろいろ追悼文が書かれたりしたのを読んでみると、僕の知ってる姿とは違うというか、この人は一体誰なんだろう?みたいになって、自分の記憶すら違う物語に書き変えられているような感覚に陥ったんです。映画を仕上げるためのポスプロ作業をするにあたって、何十回もこの映画を観るんですけど、あらためて物語的な解釈を入れなくて良かったなと思ったんですよ。なぜなら解釈がないことによってそこに投影されている人物に対して自分の記憶を投影できるから。この人はこういう人だったみたいな物語みたいなものが全く無く、そういう押し付けみたいなのが無いから、僕が持っている自分の記憶が掘り起こされる。僕以外の人も同じようにそれぞれが持っているイメージを投影する媒介になればいいんじゃないかなと思ったんです。佐々木: 亡くなる前の最後の演奏ということで、どうしてもドラマチックに観てしまいがちですよね。僕は悲壮感みたいなのがいい意味で少ないのが良かったと思いました。でも、それは裏返すと僕がそういうふうに見たくないというのもあったのかもしれませんね。
空: 悲壮感はどうしても出ちゃいますよね。本人のセンスと音楽が割と悲壮感に満ちているので。どんなにハッピーな音楽を作ろうとしても、どうしても和音の中に悲壮感が入ってしまう人だったので。だから全体的に悲しい感じになってしまう。なので、僕が唯一音楽で口出しをしたのが、最後の曲を「Opus」か「Aubade 2020」のような淡々としたものにしてくれってことだったんです。悲壮感にも満ちてないし恍惚とした気持ちに満ち溢れてるわけでもなく、本当に毎日をただ生活しているような曲で終わりたかったんです。その意図を本人もすごく理解してくれて、“分かった、じゃあ「Opus」をめちゃくちゃエモーションレスに弾く”って言って弾いてくれたんです。
空音央|監督
米国生まれ、日米育ち。ニューヨークと東京をベースに映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動している。これまでに短編映画、ドキュメンタリー、PV、ファッションビデオ、コンサートフィルムなどを監督。2017年には東京フィルメックス主催のTalents Tokyo 2017に映画監督として参加。個人での活動と並行してアーティストグループZakkubalanの一人として、写真と映画を交差するインスタレーションやビデオアート作品を制作。2017年にワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されているReborn-Art Festivalで短編映画とインスタレーションを制作。2020年、志賀直哉の短編小説をベースにした監督短編作品『The Chicken』がロカルノ国際映画祭で世界初上映したのち、ニューヨーク映画祭など、名だたる映画祭で上映される。業界紙Varietyやフランスの映画批評誌Cahiers du Cinéma等にピックアップされ、Filmmaker Magazineでは新進気鋭の映画人が選ばれる25 New Faces of Independent Filmの一人に選出された。2022年にはサンダンス・インスティチュートのスクリーンライターズ・ラボとディレクターズ・ラボに参加。
川上拓也|編集
インタビュアー:村尾泰郎(音楽/映画評論家)
村尾: 川上さんはどういう経緯で『Opus』に参加されたのでしょうか。川上: 空音央監督とはこれまで何本か一緒に仕事をやっていて、プライベートで食事に行ったりもしていたんです。それで一昨年(2022年)、監督から電話があって、坂本(龍一)さんの演奏を撮影して映画にするプロジェクトがあるんだけど編集をやってくれないか、と頼まれました。これまでの仕事を通じて、監督の仕事への向き合い方とか好みはだいたいわかっていたので軽い気持ちで引き受けたんです。村尾: 撮影前に監督は編集についてどんな話をされたのでしょう。川上: そんなに細かい話はしませんでしたが、「映画」として編集して欲しいということでした。ミュージック・ビデオみたいな感じではなく。村尾: 川上さんにとって「映画的な編集」というのはどういうものですか?川上: ショットの選択だと思います。ミュージック・ビデオの場合、音楽に合わせて映像を編集しますが、映画はショットを優先させる。今回はAカメ、Bカメ、Cカメの3つのカメラで撮影して、それぞれが撮った素材をスイッチングして(映像を切り替えて)いるのですが、Aカメのショットが“生きて”いたら1曲ワンショットでもいい。ただ、だからといってショットを絶対的なものにすると音楽とそぐわなくなることもあるので、音楽との関係を壊さないようにしながらショットを選択していきました。村尾: 音楽と映像の関係性を意識した編集だったんですね。音楽を楽しむだけではなく、坂本龍一という人物が浮かび上がってくる作品に仕上がっていました。川上: 編集する前に素材を全部観た時に、坂本さんとピアノ、坂本さんと音との関わりを描いたドキュメンタリーだと感じたんです。なので、本作はコンサート・フィルムというよりも、ドキュメンタリー映画と考えて編集しました。そして、最初に編集して見たものを議論の土台として、監督と話をしながら一緒に直して行くという感じでしたね。村尾: 1曲1曲、趣向を凝らした映像と照明で撮られていますが、その繋ぎ方にも工夫が凝らされています。暗転になったり、演奏以外のシーンが挿入されたり。そうした繫ぎ方は川上さんに任されていたのでしょうか。川上: 任されていた部分もあったかと思います。全部繋いだものを何回も観直して、その度に初めて観るお客さんの気持ちになって、ここはもう少し時間をあけて曲の余韻を味わえるようにした方がいい、とか、考えながら繋ぎました。演奏の合間にミニ・シーンが入っているじゃないですか。坂本さんが「Tong Poo」を練習したり、ちょっと疲れたような様子を見せたり。あれはカメラマンが独自の判断で撮影したものだと思いますが、そういうものを曲間に入れることで、映画としての流れが作れないかと思ったんです。村尾: そういう演奏以外の映像がライヴのMCみたいな役割を果たして、坂本さんの集中力の高い演奏からくる緊張感を和らげていますね。川上: 最初に曲だけ繋いで通して観た時に、集中度が高すぎて(笑)。このままだとすごく疲れるな、と思ったんですよ。村尾: 1人のカメラマンが撮っていたら、坂本さんとの関係性が密になりすぎて息苦しく感じていたかもしれませんが、3人のカメラマンの映像が使われていることで緊張感を感じさせながら表情豊かな映像になっているように感じました。川上: 監督と撮影監督のビル(・キルスタイン)との間で、撮影に入る前に綿密に話し合って撮影設計が決め込まれていたと思います。だから映像素材はどれも素晴らしく、監督とビルが思い描いたものをできるだけ崩さずに編集しようと思いました。ビルは技術的にはもちろんですが、カメラワークもすごいんですよ。まさにスーパーカメラマン。Bカメの石垣求さんも映画の撮影監督で、使える画を常にしっかり押さえている。何が必要かを心得ている間違いない素材なんです。Cカメの小田香さんは映画監督で自分で撮影もするんですけど、自由な感性で撮っていて。ショットの選択に迷った時はビルのショットを選べば安定するし、何かアクセントが欲しい時は小田さんのショットを入れてみる。安定した素材ばかりだったので編集作業はとてもやりやすかったです。村尾: 3人のカメラマンの個性が撮影に反映されているんですね。川上: カメラのポジションは最初に設計された通りだと思いますが、その位置からどう撮るかは各自に任されていたのではないかと思います。「Aqua」のビルのカメラがすごくて。曲の構成に合わせてカメラが動いていくのですが、そのカメラワークがずば抜けているんです。その話を監督にしたら、「Aqua」はビルがいちばん好きな坂本さんの曲らしくて、ビルの気持ちがカメラに出ているんでしょうね。あと、映画『トニー滝谷』のサントラの曲「Solitude」が演奏されるじゃないですか。『トニー滝谷』はドリー(横移動撮影)を多用しているのが特徴の映画なんですけど、石垣さんのカメラは「Solitude」の時、ずっとドリーで撮っているんですよ(笑)。村尾: 密かにオマージュを捧げていた(笑)。小田さんのショットで印象的なものはありました?川上: 坂本さんを正面から撮ったショットがあって。カメラを上下に動かして撮っているんですけど、坂本さんがフレームから外れてもどんどんカメラを上げて壁を撮ってる(笑)。本人を目の前にして、すごい勇気だと思いました。あと、映画の最初に光の中を埃のようなものが舞っている映像があるじゃないですか。あれも小田さんが撮ったものなんです。最初はすぐに演奏シーンから入る予定だったのですが、監督と話し合って、その映像を頭に入れることにしました。村尾: そんな風に、予期しないものを作品に取り入れる柔軟さが監督にはあったわけですね。川上: そういえば、「Bibo no Aozora」で坂本さんが間違えるじゃないですか。そのあとに撮った、間違わずに最初から最後まで演奏したテイクもあって、現場からもらった記録シートではそれがOKテイクになっていたんです。でも、監督は失敗してやり直すテイクを選んだ。これまでパフォーマーとして映し出されていた坂本さんが、一瞬素顔を見せる印象的な映像で僕は好きなんですけど、実は演出されていた可能性があるんですよ。村尾: というと?川上: 去年、山形国際ドキュメンタリー映画祭に監督と一緒に行ったんですけど、そこで監督と飲んでいる時に、あのシーンは坂本さんが演奏する間に、監督が〈ちょっとだけ失敗してくれない?〉と言った、という話を聞いたんです。お酒の上での冗談かもしれませんが。村尾: もし、そうだったとしたら坂本さんの名演技ですね!
川上: 編集している時は、〈失敗しているけど面白いから使って〉と言われたんですけどね。どっちが本当かは、監督が明らかにするまで永遠の謎です(笑)。村尾: 本編に使われなかった素材で印象に残っているものはありますか?
川上: 本番の撮影で「よーい、アクション!」という声をかける担当の方がいたんですけど、坂本さんはその方の「アクション!」という声では演奏には入れないみたいで。「そうじゃなくて、こうだよ!」って「アクション!」の言い方を指導するんですよ、ちょっとイラついた感じで。疲れていたこともあるんでしょうけど、そのやりとりがとても人間臭くて面白くて(笑)。その映像を使うかどうかで意見が割れたんですけど、結局、外すことになりました。村尾: 演奏のきっかけになる掛け声なのでナーバスになりますよね。川上さんは坂本さんが演奏をする姿をご覧になってどんな印象を受けました?川上: 一言で言うと「すげえな」と思いながら編集をしていました。体力的には大変だと思うんですけど、音楽に向き合っている姿に一瞬の隙も見せない。〈この演奏をフィルムに残す〉と言う強い意志が伝わってきて、気軽に引き受けたけど生半可な気持ちではやれないぞ、と思いました。一度、撮影現場にもお邪魔したのですが、VENICEという大きなカメラを使っていて、1曲ごとに照明を変えたり、ドリー用のレールを引いてカメラのポジションをセッティングし直したりするんです。そんななかで、1曲ごとにピアノにちゃんと向き合えるというのはさすがだなと思いました。村尾: 今回、この映画を通じて、改めて坂本龍一というミュージシャンに対して感じたことや発見はありました?川上: 今回、編集作業を通じて坂本さんのいろんな表情を見たのですが、一番印象に残ったのは楽しそうな顔なんです。辛そうな時もあるんですけど、映画全体を通して坂本さんは楽しそうに演奏されている。これだけ世界的に評価されて、これだけ長い間、音楽活動をされてきて、しかも、病気なのに、ピアノと一対一で向き合って演奏するのを楽しんでいることに驚かされました。村尾: 最後まで音楽に触発されていた。まさに芸術は長く、人生は短い、ですね。
川上: ほんとそうですよね。坂本さんのピアノの響きを聴きながら、今も演奏をしながら何か新たな発見をしているんだろうな、と思って。そこに終わりなき探究心みたいなものを感じたんです。それが僕にとっての発見であり、希望でした。
川上拓也|編集
2012年からフリーランスとしてドキュメンタリー映画を中心に録音技師、編集者として活動。作り手によるドキュメンタリー批評雑誌『f/22』編集委員。主な作品は『風の波紋』(16/小林茂監督)、『台湾萬歳』(17/酒井充子監督)、『アイヌ・ネノアン・アイヌ』(21/ラウラ・リヴェラーニ&空音央監督)、『マイ・ラブ 日本篇 絹子と春平』(21/戸田ひかる監督)、『百年と希望』(22/西原孝至監督)、『重力の光 祈りの記録篇』(22/石原海監督)、『はだかのゆめ』(23/甫木元空監督)、『二十歳の息子』(23/島田隆一監督)、『きのう生まれたわけじゃない』(23/福間健二監督)など。
ZAK|サウンドディレクター/エンジニア
インタビュアー:國崎晋(RITTOR BASE ディレクター)
國崎: レコーディングについて、何か坂本さんから注文はありましたか?ZAK: NHK509スタジオは響きが良いので、それを期待していると言われました。あとリヒターがバッハ「平均律クラヴィーア」をお城で録ったレコードを教えてもらって…… 坂本さんが若い頃によく聴いていたそうで、「こんな感じが好きなんだよね」と。今まではそういうリファレンスを出す人じゃなかったので、ちょっとビックリしました。若い時の体験を自分のアウトプットに反映したいっていうのはすごく素直な気持ちだし、そういう境地なんだなとも思いました。國崎: 実際の収録について伺いたいのですが、ZAKさんはレコーディングやコンサートのとき、ピアノを置く位置をとても細かく調整されますよね。ただ、今回の収録は映画の収録であり、撮影チームの意向もいろいろあったと思います。録音側と撮影側で何かコンフリクトしたことはありましたか?ZAK: 置き場所については任せますと言われました。ただピアノの蓋は付けた状態にしてほしいと。音のことを考えると蓋は取った方がいいんですが、映像的なことを優先して、取らずにレコーディングしました。実際に様々な反射が鏡のような役割をしていて、映像を立体的で美しいものにしていると思います。國崎: ピアノの蓋を外すと音が良くなるのはなぜですか?ZAK: 音が開放的になるんです。もともとピアノの蓋はステージから客席に向けて音を広げていくためのものですから、録音の場合はあまり必要無いと思っています。蓋があるとちょっとレゾナンスが生じるし、ピークも出ます。もちろん、皆さんはそれも含めてピアノの音として聴き慣れていると思うんですけど、僕はもうちょっとクリアな方が好きなんです。坂本さんもライブや録音で蓋を外されることも多かったですし、無い方が圧倒的にマイキングしやすいんですよね。マイクを自由なところに置けるし、マイクの上に蓋が無いことによってレゾナンスも起こらないから、より自然な音が録れる。ピアノという楽器の音を全体としてちゃんと録りやすいんです。國崎: 蓋を付けるということは譲りつつ、ピアノの置き位置はZAKさんの意向通りになったのでしょうか?ZAK: 最終的には僕が希望したところより少し壁側に寄って、向きも反対になりました。國崎: ZAKさんはレコーディングやコンサートで、ピアノのキャスターの下に木のスペーサーのようなものを挟むことが多いですが、今回も使いましたか?ZAK: はい。クラビベースという木でできているチューニングベースで、役割としてはインシュレーターに近くて、余分な音の鳴りを減らすために使います。おにぎりのような形をしていて、各頂点の方向に音が逃げるので、向きを変えることによってピアノ自体の音の詰まりなどを逃がしたりトーンを調整します。ピアノの複雑な機構と置かれている空間とのバランスを取るためにピアノ自身の位置や、足の角度を調整してニュートラルな状態に持っていくように流れをよくする感じです。…… 気功や整体っぽい感覚ですね。人に例えると立ち方や姿勢を調整して声の出方を良くするみたいな。國崎: ピアノの音を録るため、マイクはどのようなセッティングにしたのでしょう? そこでも撮影チームとの折衝が必要でしたか?ZAK: 位置の変更は見え方の都合で曲ごとにありました。だからすべての曲でマイクのセッティングは少しずつ変わっています。國崎: 撮影に支障がないよう、設置するマイクの本数を少なくした方がいいとは考えませんでしたか?ZAK: 最初はそう思いました。それこそ坂本さんがリファレンスとして教えてくれたリヒターの録音はワンポイントステレオで録られているような音でしたし、プロダクションの方からもそういう録音でどうかという話もありましたが、現場では何が起こるか分からないですし、映画になるなら、きっとDolby Atmosにしようという話も出てくるだろうと思い、マイクはたくさん置くことに…… 合計で27本立てたのかな。國崎: 27本もマイクを立てて、撮影チームは大丈夫だったのでしょうか?ZAK: 本数が多いことについては問題が無かったです。逆にビジュアル的にも面白がってもらえました。國崎: ダンパーペダルの音を拾っているという話がありましたが、『Opus』ではダンパーペダルの動作音がとても大きく聴こえました。ピアノってこんなにゴトゴト音がするのかと驚いた方もいらっしゃると思います。ZAK: 別に坂本さんの踏み方が荒いわけじゃなく、実際に近くで聞くとあれくらいペダルの音がするんですが、今回のミックスではその音を強調しているのも確かです。というのも、あの音を含めて坂本さんの演奏だと思うので。國崎: 昔に比べると坂本さんはピアノを弱音で弾くことが多くなりましたよね。それで相対的にダンパーペダルの音が大きく聴こえる…… 恐らくご本人も耳を澄ましてピアノを弾かれるようになったからこそ、ダンパーの音も聴きながら演奏されていたのかもしれませんね。ZAK: そうだと思います。多分、ダンパーペダルの上げ下げを記譜しようと思ったら、できると思います。上げる速度まで坂本さんは体感で調整していたと思います。國崎: ダンパーペダルと対照的に、坂本さんの呼吸音は『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』として配信されたときと比べ小さくなっていました。ZAK: 配信のときに呼吸音を大きく残したのは2つ理由がありました。1つはダンパーペダルの動作音と同様に、呼吸音や衣擦れの音も含めて、その場で起こっていることを全て音楽の一部としてとらえたいという意図がありました。もう1つは、配信された当時、坂本さんはご存命で、最後の力を振り絞って演奏していたため、その存在感とその瞬間の生々しさを感じさせ、同時に生命の儚さと尊さを静かに、強く訴えかけるような気持ちもありました。続く『Opus』のミックスでは『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022』より更に長尺になったため、情報量をフォーカスするために呼吸音は減らしていて、Blu-rayではプライベートに何度も再生されることを考慮してさらに減らしています。國崎: たくさんのマイクを使った録音だったわけですが、それらを使ってどういうミックスを作ろうとされたのでしょうか?
ZAK: 曲ごとに違うものにしました。ラストで流れる「Opus」は環状に置いた12本のマイクで収録した音をメインにしていて、ほかにも数曲それと同じような音像がありますが、あとは曲ごとにかなり違いますね。國崎: 普通でしたら音像を1つ決め、全部の曲でそれを踏襲するやり方になると思いますが、そうはしなかったと?
ZAK: 普通のライブ映像だったらそれでいいかもしれませんが、やはり映画なのでもっと強い作品として見えた方がいいだろうと思い、1曲ごとに変えていったんです。國崎: 具体的に何をポイントとして曲ごとに変えているのですか?ZAK: 編集が終わった映像とマッチするものを探していくやり方です。音先行ではなく、映像とのバランスで空間やリバーブ感を決めていきました。それが顕著に出ているのは冒頭の「Lack of Love」で、カメラが坂本さんに近づいていくのに合わせて、音量をだんだん上げています。だからすごく生っぽい仕上がりになっていると思います。國崎: それこそ映画のサウンドトラックを作っているようなミックス方法なんですね。映像に対して合うような音を、何十本ものマイクで収録されたトラックのバランスで都度都度変えていくという。ZAK: はい。なので曲の中でもクローズアップのシーンと離れているシーンとでマイクのバランスを変えています。例えば「Andata」では最初はちょっと離れた音像で始まるんですが、途中で結構寄るシーンがあるので、その時は音も近く聴こえるようにしています。國崎: クローズアップのシーンではピアノの近くに立てたマイクの音量を上げ、遠景だと遠くに置いたマイクを上げていく?
ZAK: そうですね。近くのマイクを上げるだけじゃなく、遠くのマイクの音量を減らすことで近い音に聴こえるようにすることもあります。國崎: 作品としての純度をどんどん高めるために必要な演出を施していかれたと?
ZAK: ええ。なので坂本さんの本来の演奏を一般的な録音の仕方で聴かせるという形からは離れているかもしれませんし、それに違和感を感じる人がいるかもしれませんが、その”場”を体験するという点から、没入すれば逆にそれが正しいと思うような仕上がりになっているとも思います。NHK509スタジオという空間の容積としては変わらないけれども、自分が見ている視座が変わっていくような感じですね。
ZAK|サウンドディレクター/エンジニア
幅広く多彩な音楽活動に携わり、Alva Noto、BOREDOMS、Brian Eno、BUFFALO DAUGHTER、FISHMANS、FRICTION、Jeff Mills(Spiral Deluxe)、Oneohtrix Point Never、青葉市子、UA、菅野よう子、坂本龍一、三宅純などのライブ、レコーディングを手掛け、現代美術家の村上隆との『SUPER FLAT』以降の作品の共作や、『維新派』『飴屋法水』『NODA MAP』『マームとジプシー』などの演劇の音響、犬童一心監督の『名付けようのない踊り』などの映画音楽監督、近年は片山正通の手掛けた『虎ノ門ヒルズ T-MARKET』など公共施設や店舗の音響も手掛けている。
酒井武|ピアノ調律師/コンサートチューナー
インタビュアー:國崎晋(RITTOR BASE ディレクター)
國崎: 「ピアノ調律師/コンサートチューナー」とはどのようなお仕事なのでしょうか?酒井: ピアノが使われるコンサートやレコーディングの現場で、ピアノの鳴り方をいろいろな面から調整する仕事をしています。ピアノの調律は音の高さを合わせるだけでなく、ピアノのメカニックの部分であるアクションを調整する作業も行います。ピアニストから鍵盤をもっと深く沈みこむようにして欲しいとか、逆に浅くして欲しいとか、あるいは重くとか軽くとか、タッチに関していろいろと感覚的なリクエストをいただくので、ピアノのメカニズムのいろいろなパーツを調整してそれに応えていきます。その作業のことを「整調」と言います。さらに音色を整える作業もあり、それは「整音」といいます。音の高さを合わせる「調律」、アクションを調整する「整調」、そして音色を整える「整音」、この3つをまとめて「調律」という言い方になっています。國崎: 酒井さんはどのような経緯で坂本さんのピアノを調律するようになったのですか?酒井: 坂本さんのケースはとても珍しくて…… 普通、ピアニストは自分のピアノを持ち運べませんので、ホールやスタジオの備品を使うのですが、坂本さんはレコーディングやコンサートのとき、常にご自身のピアノを現場に持ち込んでいたんです。坂本さんが所有されているピアノがヤマハピアノだったので、代々ヤマハの調律師が坂本さんのピアノの調律を担当しており、僕は2010年から2015年の5年間を担当していました。國崎: 坂本さんのピアノの調律を行う場合、他のピアニストとは異なるような注文はありましたか?酒井: 僕が最初に坂本さんの調律を本格的に担当したのは、2010年に大貫妙子さんと作られた『UTAU』のレコーディングのときでしたが、そのときに「真っ直ぐな音…… ピーンと鳴るような音が欲しい」と言われました。ピアノは1つの鍵盤につき弦が3本ある音域があって、それらをどう合わせるかによって“ポーン”とか“フワーン”というように、いろいろな音の形が作れるのです。例えばショパンを弾く場合だと“フワーン”となるように調律しますし、バッハだとカチッとした音にします。坂本さんの場合はそのどちらでもなく、“ピーン”という揺らぎのない音。コンサート会場の最後列まで真っ直ぐに届く音を望んでいました。「静かな森の中に湖があって、湖面が全然揺れてない状態」とおっしゃっていましたが、そのためには単純に3本の弦をぴったり合わせればいいというわけではありません。ぴったり合わせると減衰が早くなってしまう…… 合い過ぎて“ピーン”じゃなくて“ポン”ってなってしまうのです。國崎: 近年、坂本さんはピアノの音の消え際を聴くのが好きとおっしゃっていました。そのためには真っ直ぐな音を必要とされていたのでしょうか?酒井: はい、響きを聴きたいから音を長く伸ばすにあたり、揺らぎがないようにしたかったのだと思います。ただ、そのためにはオクターブごとに平均律が本当に精密にできてないといけない。そうでないと次のオクターブで崩れていってしまいます。坂本さんはピアノの88鍵を全部使うので、それぞれのオクターブを精密に合わせていくにはかなり時間がかかります。國崎: 坂本さんは鍵盤のタッチに関してはどのような好みがあったのでしょう?酒井: タッチに関しては、2010年から2015年に僕が担当していた時と、『Opus』の録音をした2022年とでは話がちょっと違います。2010年から2015年頃の坂本さんは、ピアニッシモからフォルティッシモまでコントロールできる体力があって、音色は暖かく落ち着いた音が好みでした。その音を出すために、それに合うタッチにしていました。ところが『Opus』収録のとき、初日に僕が前のイメージのまま整調したら、指慣らしをされた坂本さんに呼ばれて、「酒井さん、すごく僕のことを分かってくれていて、とてもいい調律なんだけど、今僕は闘病中でタッチが変わってしまったんだ…… 」と。体力が落ちていた坂本さんにとって、タッチが敏感過ぎたんですね。それで少し鈍くする方向で整調していきました。國崎: 「整音」についても以前と変化した部分は?酒井: 音色については「暗い音を出したい」と言われました。ピアノの音にはたくさんの高次倍音が含まれていて、それにより生じるブリリアントな音色は特にクラシックの演奏に必要なのですけど、暗い音を出すためにはその成分を抑え減らしていく方向で整音しました。國崎: 具体的にはピアノのどこを触るとブリリアントな成分を抑えられるのでしょう?酒井: ピアノは鍵盤と連動しているハンマーが弦をたたくことで音が鳴る仕組みになっていますが、そのハンマーの固さを調整することで、ブリリアントな音からソフトな音までさまざまな音が出せます。ソフトにするためにはハンマー外側の羊毛の部分を、針が付いている工具で刺していきます。そうすると羊毛がほぐれて柔らかい音になっていきます。逆に硬くしたい場合は鍵盤を連打して羊毛を固めたり、紙やすりをかけて削ったり、硬化剤を使って硬くすることもあります。國崎: 『Opus』収録の際、整音は曲ごとに行ったのでしょうか?酒井: 全部の曲というわけではないですが、曲ごとに弾かれる音域が少しずつ違いますからその辺りを調整することはありました。ピアノは弾きこんでいくと、さっきも言いましたようにブリリアントになっていく…… どんどん鳴るようになりますので、その辺りのバランスを直していきます。収録は一週間ほどかけて行ったのですが、実は日々音は変わっているのです。坂本さんの望んでいる音が分かってきたというか、僕の耳が変わっていったというのもありました。『Opus』のコンセプトのひとつとして時間の流れがあるので、坂本さんも「ずっと同じじゃなくていいんだ」っておっしゃっていて、僕もどんどん良くなるように毎日調整を重ねていきましたね。國崎: 収録順と映画での曲順はほぼ一緒と伺いました。酒井: はい。なので、曲を追うごとにだんだん楽器が鳴ってきています。最初にその状態のピアノが作れればいいんですけど、その時間があってこそなので。逆に曲ごとのそういう聴き方を楽しんでいただければ嬉しいです。國崎: 「20180219 (w/prepared piano)」はプリペアードピアノによる演奏でした。映像にもありますように坂本さんが施したのですよね。酒井: はい、弦をクリップで挟んだり、いろんな小物を差し込んだりしていましたね。國崎: プリペアードピアノは、ピアニストが偶発的な音が欲しくて行うケースが多いですが、「20180219 (w/prepared piano)」は本来のピアノとは違う倍音を得るために坂本さんが「整音」をしているように見えました。酒井: その通りですね。ちゃんと狙いがありました。恐らく何回も試したのを踏まえ、クリップの挟み方などのノウハウが坂本さんにたまっていたのだと思います。出鱈目にやっているのではなく狙って出していましたね。國崎: 完成した『Opus』をご覧になって、酒井さんはどんな感想を持たれましたか?
酒井: 2022年末に「Playing the Piano 2022」の配信を観たときと、映画『Opus』とで印象がかなり変わりました。お亡くなりになったという意識で観ているからかもしれませんが、より純度が高いというか、ドキュメンタリー性を減らし、作品性が高まったと思いました。冒頭、カメラが坂本さんの後ろ姿をとらえていますが、あのアングルは僕がいつも見ているアングルなのです。コンサートでのいつもの自分の立ち位置から見える景色なのでドキドキしましたね。國崎: 坂本さんの最後のピアノ演奏として残るかもしれないという意味で、大変なプレッシャーだったとは思いますが、あらためて振り返るといかがでしたか?
酒井: 普通のコンサートとは違い、事前の配信もするし、最終的には映画のための収録で、坂本さんからも「これは大切な収録だから酒井さんにお願いしたんだ」とお話をいただき、嬉しい反面、気を引き締めて頑張らなければならない現場でした。2015年以降、僕は海外に転勤となって坂本さんの調律から離れていたのですが、今回また呼んでいただけたのは、僕が坂本さんの調律をやっていた5年間は『UTAU』の収録やツアーだったり、「Playing the Orchestra」など、ピアノを弾かれる機会がものすごく多い時期で、そのときの印象が良かったからだとスタッフの方から伺いました。それこそ最初の『UTAU』の収録のときは、“真っ直ぐな音”と言われてもすぐに対応できず、「もうちょっとこうして」みたいに言われていたのが、だんだんと何も言われなくなり、僕も坂本さんが求めている音が分かってきて、担当していた時期の後半3年くらいはピアノについては何も言われることがなくなりました。クラシックの現場で得たものに加え、学ぶことが多く、そういう意味では坂本さんに育ててもらったという意識があります。そんな坂本さんにとって最後になるだろうという収録で再び呼んでいただけたのは本当に嬉しかったです。一週間かけた収録は、やっている時は大変だったのですけど、終わってみると本当に充実した毎日でした。
酒井武|ピアノ調律師/コンサートチューナー
神奈川県伊勢原市出身
空音央|監督
インタビュアー:佐々木敦(思考家/批評家)
佐々木: そもそもなぜライブ演奏を音央さんが映画にすることになったのですか?空: 発端は2020年に行われた配信ライブで、僕は一応カメラ担当で入っていたんですけど、実際に配信されたものの出来が良くなかったんです。で、2022年の3月か4月に“コンサートみたいなものを映像化したいから何かやってくれ”という話が来たんです。僕はちょうど自分の長編映画の準備段階で忙しい時期だったんですけど、本人の病状がどんどん悪化していたので、やはり後悔はしたくなかったのでやることにしました。佐々木: ということはディレクションというか、どういうルックのどういう作品にするかを考えるところから始めることができたわけですね。演奏を撮影して映画にするといっても、本当にいろんなアプローチがあり得えますが、こういう形の作品にしようとした理由は?空: 最初は悩みました。ドキュメンタリー的な映像…… 最期の日々的なものを撮ってコンサート映像に挿し込んだりとか、アーカイブ映像を持ってきたりとか、インタビューを挟んだりとか、もしくはコンサートのビハインド・ザ・シーンみたいな、ちょっとほっとしている雰囲気の映像を挟むとか、いろいろありますよね。でも、ある時点でそれはいらないって決めたんです。佐々木: それはすごく大きな選択だったと思うんですけど、なぜそうされたのですか?空: 自分が肉親という特権的な距離にいるからこそ撮れる映像を入れれば、もちろん本人の人間性みたいなものが見えてくるんですけど、実はそれって既に結構やられている。だから僕にできる一番のことは、ちゃんとコンサートを撮ることかなと。実際、コンサートを疑似体験するっていうのを目的とした途端、いろいろスムーズにいったんです。とにかく現場で起こったことを撮るだけにして、どれだけこの映画を通してコンサートを疑似体験できるかに徹する感じ。そうと決めたら僕の仕事は単純というか…… 今でも思っているんですけど、僕は本当にこの映画の監督なのかなと。音楽の方はほとんど口出しせず、映像だけ任せてもらって…… 映像も本当に信頼しているビル・キルスタインっていう撮影監督に任せ、あとは素晴らしい照明デザインの吉本有輝子さん、信頼する編集の川上拓也さん、カメラオペレーターの石垣求さん、小田香さん、そして録音とミックスのZAKさん。みんなすごく信頼しているスタッフなので、ほとんど任せた感じなんです。佐々木: 信頼できるスタッフに任せたとはいえ、監督として何かテーマ設定をされたのではないですか?空: そうですね、やはり核に据える何かがないとブレるので、“身体性”をテーマとしました。それを決めたというのが監督としての自分の仕事ですね。そうしたらすぐにほかの要素が決まりました。例えば、なぜ白黒の映像にしたのですかとよく聞かれるんですけど、それも身体性を考えたからです。白黒にすることで手の皺やピアノの質感を浮かび上がらせることができる。あと、最も本質的な映画の喜びは何か?みたいなことを考えたとき、僕は炎を見てるような光と影が揺れている感じ…… しかもそれがリズムに乗ってというのが一番だと思っていて、それを白黒でやるとレジェの『バレエ・メカニック』みたいな初期のダダ作品とか、アルタヴァスト・ペレシャンのモンタージュ理論に近いような、白と黒の影のダンスみたいになっていくかなと。しかもズームインすればするほど、影が大きなスクリーンを巡るだけみたいになって抽象性が増すかなと。佐々木: 抽象性というか、今回かなりストイックな作品になることは最初から分かっていたと思います。NHKの509スタジオで撮影されたわけでお客さんはいない。広いNHKのスタジオにピアノだけで、ものすごく要素がミニマルになってしまうじゃないですか。それを長編映画にするとなると映像設計が必要というか、ずっと同じ感じで行くわけにもいかないですよね。何か過去の映像作品で参考にしたものはありましたか?空: 具体的に参考になったのは『グレン・グールドをめぐる32章』という、いろいろな切り口でグレン・グールドを見せる映画でした。ピアノを撮る場合って結構アングルが限られるんですけど、こんな撮り方があるんだという発見がありましたね。もうひとつはやはりグールドものなんですけど、1960年代にレナード・バーンスタインがやっていたアメリカのTV番組にグールドが出演したときの映像Ford Presents "The Creative Performer" (1960)です。オーケストラと一緒に演奏している映像で、白黒なんですけどちゃんとライティングされていて、ハリウッドさながらのミュージカル映画みたいなカメラの動きが素晴らしいんです。こういう感じに撮れば長く観ていても飽きないなと。佐々木: そういうリファレンスがあった上で、実際にはどのような撮影プランを考えたのですか?空: 観客がいないというのを逆に生かして、いかに観客の主観的な体験をカメラで模せるかを考えました。例えばホールのコンサートって大体何百人と一緒に聴くものですけど、次第に自分の世界に入っていって、気付いたらすごく近くにいるような錯覚に陥ることってありますよね。逆に広大なメロディに差し掛かった時に本当に風景が見えてくるみたいな感覚に陥ったりも。そんな感じで曲に寄り添った撮影をしたいと思ったんです。佐々木: 曲そのものが持っているイメージとか展開を踏まえ、そのドラマツルギーみたいなものを映像に反映させたということですか?空: まさにその通りですね。ショットの構成を曲単位でやりました。分かりやすい例で言うと「Aubade 2020」という曲は全部固定カメラでやったんですけど、ビルに“これは淡々とした毎日の生活みたいな曲だから、小津っぽく撮ってくれ”ってお願いしました。佐々木: 観客の主観的な体験を模すようなカメラということでしたが、オープニングの「Lack of Love」は舞台袖からのカメラで、観客目線とは異なりますよね。空: そこだけは例外というか、あれは僕の視点なんです。本人がピアノを弾いてる時に僕が一番見ていた視点は背中からだったので、それを最初にしました。何がもとになってるかっていうと、坂本龍一がまだ元気だったころ、“ご飯ができたから呼んできてよ”って母親に言われて僕が階下のスタジオに呼びに行くんですけど、大体ピアノを弾いているかパソコンをいじってるんです。で、ピアノを弾いていると邪魔しにくい…… 泣いたりしているんですよ、自分の曲で。ホントに恥ずかしげもなく…この人逆にすごいなと思ったりするんですけど、ご飯ができてるから声かけなくちゃって、“ここにいるよ”みたいに自分の存在を感じさせて…… オープニングのシーンはそういう視点なんですよね。佐々木: 実際、「Lack of Love」は最初は結構距離があるところから背中を追っていって、それがここまで寄るんだっていうくらいのとこまで寄って、ピアノの音もだんだん大きくなる。実際にはカメラとマイクで収録しているわけですけど、人みたいだなと思ったんですよね。演奏している人が気付いていないのを後ろからそっと行く感じ。それが冒頭にあることによって没入させるというか、まるで自分が本当にその場に立ち会って演奏していくさまを見続けている感じになる。その一方で、これは監督の音央さんの視点というか主観でもあるなって思ったんですよ。主観を観客の視点に開け渡すっていう部分と、音央さん自身のパーソナルな感覚みたいなものが二重になっている感じで、それがすごく感動的でした。空: そこまで見ていていただけると嬉しいですね。佐々木: 全編白黒にした理由は先ほどうかがいましたが、その中でも光…… 照明の変化が印象的でした。空: 撮影の構成はほとんど曲単位でやっていたので、全体の流れは照明で作りました。薄暗いところから始まり、4曲目、5曲目で朝3時とか4時に水平線がちょっとだけ明るんでいる感じになり、「Aubade 2020」でだんだん白んで朝になったと知らされる。佐々木: 光の変化によって“時間”というテーマも浮かび上がってきますよね。坂本さんの最後のシアターピースは「TIME」でしたし、ご本人にとっても大きなテーマだと語られていました。面白いなと思うのは、この映画は103分の長さで、その103分の中に照明で表されているもっと長い時間がたたみ込まれている。さらに言うと撮影は何日にもわたって行われたわけですから、1つの作品の中に複数の時間の層があるわけです。実際に撮影は何日間行われたのですか?空: 8日間プラス準備に1日でした。佐々木: 8日間の撮影は連続していたのですか?
空: はい。なるべくセットリスト順に撮ったんですよ。それができたから照明による時間変化とかも考えやすく、クリエイティブな作業ができました。佐々木: 8日間の撮影を経て、いろいろな映像が撮れたと思うのですが、それを編集していくとなるとかなり選択の幅があって大変だったのではないですか?
空: 実はそんなに大変じゃなくて…… 編集者の川上拓也がすごい優秀だっていうこともあるんですけど、彼に言われたのは、僕とビルの撮影の設計があまりにも決まり過ぎていて、これ以外に編集のしようがない…… “こう使ってほしいって映像が言ってる”と言われました。佐々木: 肉親である音央さんだからこそ、神格化したくないという気持ちもあったと思いますが、実際このように1本の映画として仕上がったら、そこからまた新たに伝わるイメージとか増幅されるイメージもあると思います。そこは多分すごく悩まれたんじゃないですか?
空: ええ…… 実際どんな人間だったかということなんですが、死んだ後にいろいろ追悼文が書かれたりしたのを読んでみると、僕の知ってる姿とは違うというか、この人は一体誰なんだろう?みたいになって、自分の記憶すら違う物語に書き変えられているような感覚に陥ったんです。映画を仕上げるためのポスプロ作業をするにあたって、何十回もこの映画を観るんですけど、あらためて物語的な解釈を入れなくて良かったなと思ったんですよ。なぜなら解釈がないことによってそこに投影されている人物に対して自分の記憶を投影できるから。この人はこういう人だったみたいな物語みたいなものが全く無く、そういう押し付けみたいなのが無いから、僕が持っている自分の記憶が掘り起こされる。僕以外の人も同じようにそれぞれが持っているイメージを投影する媒介になればいいんじゃないかなと思ったんです。佐々木: 亡くなる前の最後の演奏ということで、どうしてもドラマチックに観てしまいがちですよね。僕は悲壮感みたいなのがいい意味で少ないのが良かったと思いました。でも、それは裏返すと僕がそういうふうに見たくないというのもあったのかもしれませんね。
空: 悲壮感はどうしても出ちゃいますよね。本人のセンスと音楽が割と悲壮感に満ちているので。どんなにハッピーな音楽を作ろうとしても、どうしても和音の中に悲壮感が入ってしまう人だったので。だから全体的に悲しい感じになってしまう。なので、僕が唯一音楽で口出しをしたのが、最後の曲を「Opus」か「Aubade 2020」のような淡々としたものにしてくれってことだったんです。悲壮感にも満ちてないし恍惚とした気持ちに満ち溢れてるわけでもなく、本当に毎日をただ生活しているような曲で終わりたかったんです。その意図を本人もすごく理解してくれて、“分かった、じゃあ「Opus」をめちゃくちゃエモーションレスに弾く”って言って弾いてくれたんです。
空音央|監督
米国生まれ、日米育ち。ニューヨークと東京をベースに映像作家、アーティスト、そして翻訳家として活動している。これまでに短編映画、ドキュメンタリー、PV、ファッションビデオ、コンサートフィルムなどを監督。2017年には東京フィルメックス主催のTalents Tokyo 2017に映画監督として参加。個人での活動と並行してアーティストグループZakkubalanの一人として、写真と映画を交差するインスタレーションやビデオアート作品を制作。2017年にワタリウム美術館で作品を展示、同年夏には石巻市で開催されているReborn-Art Festivalで短編映画とインスタレーションを制作。2020年、志賀直哉の短編小説をベースにした監督短編作品『The Chicken』がロカルノ国際映画祭で世界初上映したのち、ニューヨーク映画祭など、名だたる映画祭で上映される。業界紙Varietyやフランスの映画批評誌Cahiers du Cinéma等にピックアップされ、Filmmaker Magazineでは新進気鋭の映画人が選ばれる25 New Faces of Independent Filmの一人に選出された。2022年にはサンダンス・インスティチュートのスクリーンライターズ・ラボとディレクターズ・ラボに参加。